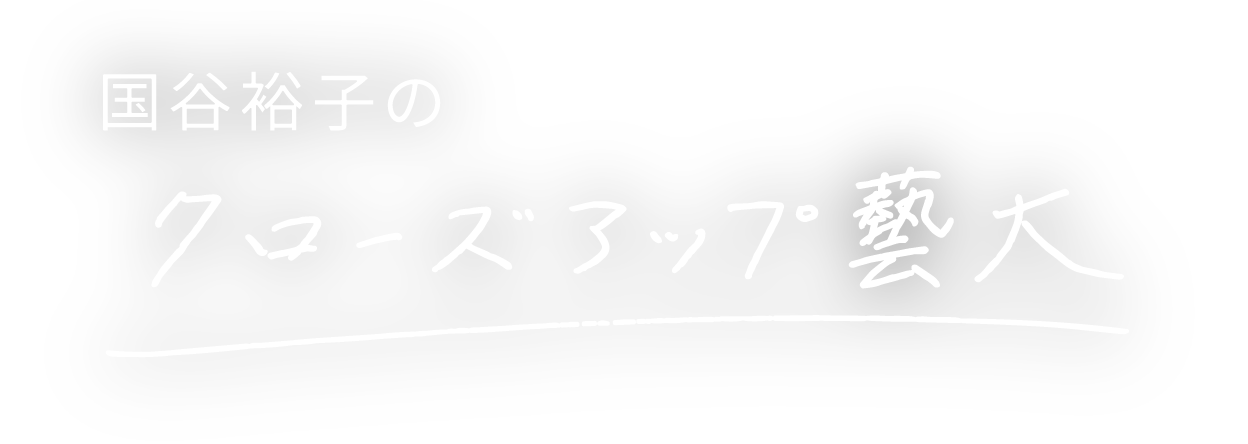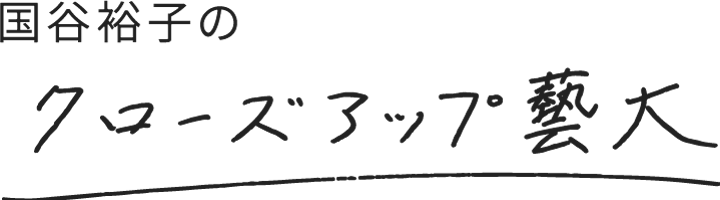第十四回 廣江理枝 音楽学部器楽科(オルガン)教授
オルガンの最初の一音にびっくりした
国谷
廣江先生とオルガンの出会いは、青山学院の中等部の入学式。すごい衝撃を受けたそうですね。
廣江
どんな感じだったかはよく覚えていないんですが、衝撃を受けたのは覚えています。「なんでしょうこれは?!」っていう。鍵盤楽器には見えるので、何か弾くんだろうなと思ったんですが、最初の一音が鳴り始めた時に、すごくびっくりして。それまで私のなかに無かった楽器でした。本物のパイプオルガンではなく電子オルガンだったところがちょっと恥ずかしいんですけれど…。大きい音が出せることとか、足でも鍵盤を弾くところが衝撃だったんだと思います。
国谷
きれいだったとか美しかったとかではなく?
廣江
本当に覚えていないんです(笑)。いい悪いではなく、びっくりしたことは覚えていて。でもそれがあの楽器に出会うきっかけだったんです。あの楽器に自分が何か関わろうっていう。
国谷
小さい時からピアノを習っていたそうですね。
廣江
はい。大学も多分ピアノで進学するのだろうなと思って中学に入ったんですが、あのときのオルガンは、やはり衝撃だったんです。
国谷
それでやってみようという気になって、実際にオルガンの授業をとり、ピアノのレッスンも続けていらっしゃった。
廣江
はい、ピアノも続けていましたけれど、中学?高校時代って、すごくいろんなことに興味があって、ある意味ピアノに不熱心でした。中学のときは、オルガンをやるチャンスだと、かなりのめり込んでやっていたはずなんですが、悲しいかな、かなり自己流で、もうちょっとちゃんとやっていたら今頃もう少しましだったんじゃないかと思うこともあります。
高校は校舎も違うし、全く違う環境だったので続かなかったですね。その当時は授業もクラブもありませんでしたし、礼拝で弾くしかなかった。礼拝の奏楽をするという条件なら弾いてもいいみたいなことを当時の先生に言われて。それが嫌だったんだと思います。
国谷
でも毎日礼拝があってそこで聞いていらっしゃった訳ですね。
廣江
はい。そうこうするうちに大学受験が近付き、オルガンどころではなくなりました。
私はその当時クリスチャンではありませんでしたし、礼拝で弾くのも嫌だというくらいだったので、オルガンをしても食べて行けないと考えて辞めました。
国谷
キャリアを考えていたのですか?
廣江
そうだと思いますね。ピアノだから食べて行けるかというとそうでもなかったんですが、当時はオルガンのあるコンサートホールもそんなに無いし、オルガンを弾くには教会しか無かった。
当時はティーンエイジャーですから、反発心みたいなのもあって、「礼拝で弾く条件があるなら辞めます!」みたいな。

今を逃したらだめだという気持ちで
国谷
それで桐朋学園音楽大学でピアノ専攻に進まれて、大学4年生のときにオルガンと再会したのですね。
廣江
教職課程をとっていたので、大学4年のときに母校の青学へ教育実習に行きました。そしたらそこにオルガンがあった。電子オルガンですけど。「ああオルガンがあるや」って。大学も4年間修めることができそうだし、ピアノを弾きながらオルガンをもう1回やってみてもいいかなって、そのときにちょっと思ったのがきっかけでした。
国谷
趣味にしようかな、くらいの感じだったそうですね。
廣江
最初は趣味みたいな感じでした。ただ、そういうときって人生に何度かあると思いますけれど、ある瞬間にある出会いがある。やろうと思ったらトントン拍子に進んだんです。
国谷
どういうことですか?
廣江
大学4年生の6月に教育実習に行って、9月か10月くらいからオルガンの練習を始めて、3月に卒業すると同時に藝大の別科に入り、その2年後には大学院に受かった。ちょっと今から考えるとあり得ないんです。というのは、今は大学院の入試は奏楽堂でやりますが、当時は奏楽堂がまだ無かった。この楽器を弾きこなすって相当大変なことで、学部の4年間をここで学んだ人じゃないと相当難しい。でも当時はそれほど難しくはなかったので、入れてしまった。
もちろんがんばったんですけれど。「やらなくちゃ、今を逃したらだめだ」という気持ちが強くて。その気持ちは、もはや趣味ではなかったですね。別科、大学院、留学、コンクール、そこまで知らないうちに転がって行った感じがあります。
努力をしようという気持ちになったのは、自分でもわからない何かがあって、キリスト教的に言えば「召命」だったのかもしれないし、運命だったのかもしれない。人生にはいくつかそういう場面が用意されているんだなあって、実感しました。
国谷
大学を卒業したあとに実技主体の2年コース、別科に入って、そこからがむしゃらにやったということですが、その時すでに22歳ですか?
廣江
そうですね。だからそういう年齢的な、「今やらなきゃ、早くやらなきゃ」という気持ちは強かったです。コンクールは年齢制限がありますし、学校も年齢制限があるところがある。そういうリミットがあることもいい意味でプレッシャーだったのかもしれません。当時の私にとってはものすごいプレッシャーでしたけれど。

シャルトル大聖堂国際オルガンコンクールにて
国谷
1998年にフランス?シャルトル大聖堂国際オルガンコンクールでアジア人で初めて優勝されました。これは転機ともいえる出来事だったのではないでしょうか?
廣江
シャルトルのコンクールは35歳がリミットで、当時私は33か34歳かな。リミットに近い年齢でした。
国谷
大きなチャレンジでしたね。
廣江
ああいった国際的なオルガンのコンクールでアジア人や日本人が一位になることは、それまであんまり無かったんです。変な言い方ですけれど、「普通にできることなんだ」って思ってもらえるきっかけになったかなって。実際にその後シャルトルで、日本人が3人優勝しているんです。私が教えた人ばかりではないんですが。日本人でもできると思ってもらえたことのほうが、私にとっては転機でしたね。
国谷
その後はヨーロッパを中心に演奏活動をされていました。
廣江
そうですね。その後、子どもが産まれたりしたので細々と演奏活動をしつつ、藝大からお話をいただいて2006年に帰って来ました。
日本人のメンタリティはドイツでは通用しない
国谷
それまでやっていなかった楽器を22歳から本格的に始めて、世間で認められるレベルになろうとチャレンジすることは、かなり勇気のいることだと思います。
廣江
そのときは誰かに認められようとか、世界的になってやろうなんて野望は全然ありませんでした。とにかく好きで、目の前にあることをひとつずつやっていった感じです。
当時は奏楽堂も無かったですから、大きな空間で弾くこともできないし、朝から晩まで弾くことも絶対にできない。皆で楽器を分け合っていましたから。それがやりたくてドイツに行きました。向こうに行ったらいくらでもオルガンがあるので、もうそれだけのために行ったと言っても過言ではないかもしれないですね。
国谷
ドイツ留学で何が一番大変でしたか?
廣江
今は慣れたし、向こうの生活が長かったので対処の仕方がわかるんですが、やっぱり怖かったです(笑)。ドイツ語という言語がそうなのかもしれないですけど、はっきり言うし、ものすごいキツい言い方をします。日本みたいに婉曲に聞いたら答えが返ってこないし、いい答えには結びつかないので、単刀直入に言わないといけない。日本でそれをやると本当に嫌な人になってしまうので(笑)。そのチェンジが難しいですけど。
国谷
11年ドイツにいらして日本に帰ってきたときは、葛藤があったっそうですね。
廣江
はい、私は日本人じゃなくなっていたんです。何もかもが、本当にそうでした。
今となればバカだったなって思うんですけど…。学生がレッスンにやってきて、「お願いします」って言いますよね。「何をお願いしているの? 私は仕事でやってるんだけど」って、本気で思ってたんです(笑)。それが一事が万事で。
まだドイツに住んでいた頃、一時帰国したときに手に入れたい楽譜があって図書館に行ったんです。日本人の作曲家の、そこにしか所蔵していない楽譜でした。そうしたら窓口の人に、ルールで著作物の半分しかコピーできませんと言われた。「それは演奏させたくないってこと?」って思って。ドイツでそういう質問をしても別に何も起こりません。「そうかもしれないわね」ぐらいの答えが返ってくるのが関の山で、それに慣れていたんです。それで、「演奏させたくないってことですね?」って軽く言ったら、その人が泣いちゃったんです。日本人のメンタリティってこれだって。思いやりがあって、空気を読む感じ。それはドイツでは全く通用しないというか、それをやっていると話が前に進まない。
国谷
自分が求めるもの、自分が必要なものに対してはきっちり主張しないといけないし、聞かれた側も説明しないといけないという常識が欧米にはあると思います。これではなぜ半分しかコピーできないのか、理由がわからないですよね。

廣江
そうですよね。そのときにきちんと説明してくだされば、しょうがないわね、で終ったと思うんですけど、そういうことを係の人が自立心をもって説明できない。そういう日本人に対する葛藤が多々ありました。でもそのときはしょうがないじゃ終わらせられなくて、助手の人に残りの半分をコピーしてもらいました(笑)。
国谷
今はどうですか?
廣江
今は慣れて両刀遣いになりました。コロナ前は本当にしょっちゅう行ったり来たりしていたので、あっちにいたらこう、こっちに帰って来たらこうって、使い分けられるようになりました。それもどうかと思いますけれど。
対等にレッスンをするのが理想
国谷
留学したい人はたくさんいると思いますが、行ってみたものの言葉や文化に慣れなくて挫折する人もいると思います。ご自分のドイツでの経験も踏まえて、オルガンを学ぶ学生たちに何を大事にしてもらいたいですか?
廣江
留学先でうまく馴染めない日本人がいるのはすごくよくわかります。オルガンは、特にヨーロッパ的な楽器だと思うんですね。がさつというか、ざっくばらんにならないとオルガンはなかなか弾けない。
国谷
緻密じゃなくて、ざっくばらんでないと弾けない! どういうことですか?
廣江
元々、即興演奏が主流の楽器だったこともあると思います。教会で礼拝をするときに、即興的な音楽を差し挟むことは今でも行われています。オルガニストは、その場でパッと演奏するという伝統があるので作曲もできなくてはいけない。それは緻密でもできるんですけど、ある意味ざっくばらんでないと臨機応変に対応できない。あまりひとつのことにこだわり過ぎると、即興ができなくなっちゃうんで、皆さんすごくざっくばらんです。
国谷
学生たちには何を大事にしてもらいたいですか?
廣江
そうですね。留学する、ヨーロッパに行く人はそういう両面性を身に付けなきゃいけないと思います。向こうでやっていけるワイルドさっていうんですかね。言われたら言い返すような。
国谷
そういうことを教えていらっしゃる?
廣江
いや、教えていないです(笑)。
国谷
普段の授業でも言い返すように教えているのかと思って(笑)。
廣江
言い返して欲しいんですけど、最近の学生は言い返さないです。本当に皆さん従順で。「わかってるの?」って聞いても、みんな「はい」ってその通りにやろうとする。それはある意味いいことかもしれないのですが、同僚の先生たちとお話すると、「昔はそうでもなかったよね」っておっしゃる方もいらっしゃるので、ここ最近の若い人の傾向かもしれません。空気を読んで忖度というのは社会的な傾向でもあるし。でも、ヨーロッパでそれをやっていたら、とてもじゃないけど何も教えることができないですね。
国谷
でもワイルドになってほしいというのは、ひとつ大事なメッセージですね。
廣江
なんていうか、一対一の大人としてレッスンをするのが理想なのですが、学生が「お願いします」ってレッスン室に入ってきた瞬間に、「あ、違うんだな」と感じて、葛藤が始まったわけです。それは変えようと思ってもなかなか変えられない。日本の年功序列的なものは根が深い。
先輩の先生に、「『お願いします』は洗練された『こんにちは』っていう言葉なのよ」って諭されまして、それからは「そっか」って思うようにはしています。

国谷
でも廣江先生も学生のときは、「お願いします」と言っていたのではないですか?
廣江
言っていたと思います(笑)。
国谷
ドイツでは年齢が違っても対等ですか?
廣江
はい。もうすごいですよ。ドイツで教えていたときは、「口を動かす前に手と足を動かしなさい」って言いたくなる生徒がいっぱいいました。口ばっかりで生意気なんです(笑)。平気で先生を言い負かすし。
それが国民性なんですよね。自我を持って、できなくても主張をする。すごく重要なことですけど、「やることやってから言ってちょうだい!」って言いたい気持ちにはなります。
国谷
そのギャップは大きいですね(笑)。
廣江
はい。若い人たちの傾向は日本と真逆です。
国谷
グレタ?トゥーンベリさんとか、いま世界の脱炭素運動を動かしているのはヨーロッパやアメリカの若い人たちですからね。日本はほとんど若い人のムーブメントが起きない。
廣江
そうなんですよ。どうしてでしょう? 島国だから?
国谷
やっぱり出る杭は打たれちゃうからでしょうか…。
今はどこで弾いても楽しい
国谷
「大学4年でオルガンを始めて藝大に来てから水戸芸術館のホールに毎週末通うようになって、何十回と演奏する機会を与えてくれた。その頃は情熱であふれかえっていた」と書かれています。そのときの幸福感、自分が本当にやりたいことを見つけたときの喜びは大きかったでしょうね。
廣江
はい、そうですね。今はだいぶ慣れてきたというか、私にとって日常的な楽器になりましたけれど、今でも一日中オルガンを弾ける日は、やっぱりうれしいです。「ああ、弾けるんだ今日は」って。
オルガンって残響とセットにして音楽なんですね。ドイツには、最後の音を放してから7秒くらい残響がある教会があって、それが好きでした。「残響が無ければオルガンじゃない」ぐらいに思っていたので、日本に帰ってきたときは奏楽堂で弾くことさえ「つまんないな」って思っていました、すみません(笑)。でも歳をとるとともに受け入れるようになっていったので、今はどこで弾いても楽しいです。ポジティーフ?オルガンで狭い部屋で弾くのも楽しいですし、本当にそれは幸せだと感じます。
 ポジティーフ?オルガン
ポジティーフ?オルガン
国谷
教会でも弾いていらっしゃいますよね。
廣江
はい。大きな教会で、夜ひとりで誰もいないところで弾くのも気持ちいいですね。
でも、いよいよ、ひとりで弾くこと以外から学びたいと思って。私の場合はこれまであまりアンサンブルをする機会がありませんでした。もちろん、通奏低音でバロック時代のものをやってきたこともあるんでしょうけれど。それで、毎年やっている「上野の森オルガンシリーズ」の演奏会で今年はアンサンブルだけをやると決めまして、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、ホルン、オーボエの先生方をお招きし、アンサンブルをすることになりました。皆さんはオーケストラとかデュオとかトリオとかで「合わせる」ということをいっぱいやってらっしゃいますけど、私はあまりそういう経験がないので、たくさんのことを学びたいなと思っています。
国谷
がんばっていただきたいと思います。本日はありがとうございました。

【対談後記】
オルガンの演奏会で聴衆は舞台の高いところで演奏するオルガニストの後ろ姿を見つめる。オルガニストの表情や演奏中の手や足の動きは容易にはわからない。
今回、オルガンを演奏する廣江先生を収録した映像をあらかじめ観て、荘厳な調べからは想像していなかった、オルガンと格闘する姿を知りました。左右の手と左右の足が手鍵盤と足鍵盤を押しながら動きまわり、ひとりで大きな楽器を操るその姿から体形の大きい方というイメージが生まれていたので、インタビュー場所となった奏楽堂のホワイエに思いのほか小柄な方が登場し少し驚かされました。でも、お話を伺ううちに、心に秘めた力強さが次第に伝わってきました。
「世界的なオルガニストになりたいという野望はなく、とにかく好きで大きな空間で時間の制限なくオルガンが弾きたいという一心でドイツに留学をしました」「一日中オルガンの練習をしながら過ごせる日はとっても幸せです」と大きな笑みを浮かべて話されていたのが印象的でした。
【プロフィール】
廣江理枝
音楽学部器楽科(オルガン)教授
1988年桐朋学園大学音楽学部演奏学科ピアノ専攻卒業。1995年東京藝術大学 大学院音楽研究科修士課程器楽専攻オルガン修了。DAAD(ドイツ学術交流会)、アサヒビール文化財団より奨学金を得て、ドイツ国立ハノーファー音楽大学ならびにシュトゥットガルト音楽大学へ留学、ソリスト課程を卒業。オルガンを廣野嗣雄、ウルリヒ?ブレムシュテラー、ルドガー?ローマンの各氏に師事。
1998年アジア人で初めてフランス?シャルトル大聖堂国際オルガンコンクールにて優勝。デンマーク?オーデンセ国際オルガンコンクール優勝、及び武蔵野市国際オルガンコンクール最高位受賞のほか、ブルージュ古楽国際コンクール、ライプツィヒ国際バッハコンクール、プラハの春国際コンクール、ニュルンベルク国際オルガン週間コンクールなど数多くの国際コンクールで入賞。
シャルトルでの優勝以降、ドイツを拠点にコンサート?オルガニストとしてヨーロッパ、アメリカ合衆国、日本の各地で演奏会を行った。
2006年帰国。東京藝術大学音楽学部オルガン科主任として後進の指導に携わりながら、国内外での演奏活動を行っている。国際コンクール審査員やマスタークラス教授として海外からの招聘も多い。東京藝術大学教授、一般社団法人日本オルガニスト協会理事、日本オルガン研究会会員、ドイツ語福音教会Kreuzkircheオルガニスト。
CDに「ガルニエ?オルガンのひびき」(東京藝術大学出版会)、「バッハ讃 J.S.バッハ 青年期のオルガン作品」(アールレゾナンス、『レコード芸術』6月号特選盤)がある。
撮影:新津保建秀
- 1
- 2